※この記事は、第14回人生100年社会デザインフォーラム(ゲスト 長谷川櫂様(俳人)、財団代表理事 牧野篤氏との対談)から抜粋したものです。
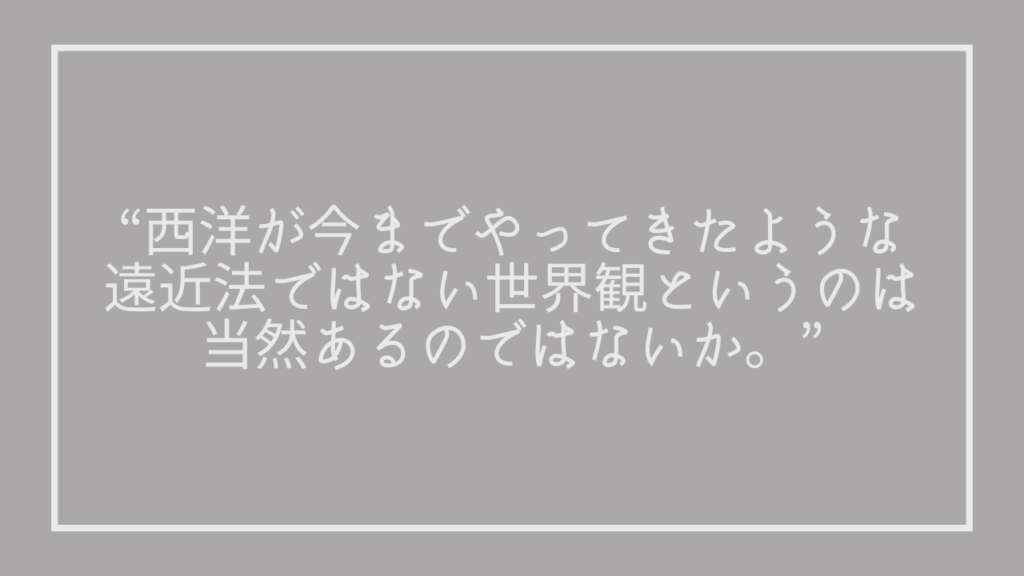
牧野先生 今日は長谷川櫂様の『和の思想 日本人の創造力』(岩波現代文庫)の中身を御紹介いただきながら、いろいろなお話をさせていただければと思います。
最初に、この本を読ませていただいて感じたのは、この「和」という言葉、長谷川さんが扱ってらっしゃる「和」というのは、例えば和が、または日本がすばらしいと言えば言うほど日本主義的な話というか、日本だけがすばらしい・特殊だというような議論になりがちかなと思って読んでいたらそうではなくて、“日本“とか“国”とかそういう狭いものを超えるものとして、受け止めていらっしゃった。
また、『俳句と人間』(岩波新書)に書かれてあった、混沌としたものから何かを生み出していく力みたいなものが和というものにもあるということで、つながってくるのかなというふうに思って読ませていただきました。
混沌としたものから何かを生み出していく力みたいなものが和というものにもある
長谷川様 日本人の持っている本当の創造力というのに日本人が気づいていないというところは可笑しくもあり悲しくもあります。
日本にもともとあったものはほとんどなく、あるとすれば海と山ぐらいしかないのですね。そこに人間がやってきて、それとともに色々な文化が入り込んで、この国に合うように作り変えていった。それが和の力、「和の創造力」と呼んでいるのですが、和室・和食とかは創造力が作り出した一つの結果があって、それを和と勘違いすると、和というのを固定的に考えてしまことになると思います。
だからもう少し元へ戻って、自分たちの文化をつくり上げる力とは一体何か?つまり、和の力とは何かというのを考えた方が、日本のためにもなるのかなというふうに思うのです。
自分たちの文化をつくり上げる和の力とは一体何か?
長谷川様 そこを見ていくと非常に面白いことがわかって、日本は島国だから自分で自分たちを内向的な人間だと思い込んでいるところがあります。でも実はものすごい外に対しての関心があり、何かいろいろなことを知りたがっている。おそらく昔からそういう民族なのですね。
平安時代のことを考えても、源氏物語に書かれていますが、あれは要するに中国の王朝を一つのモデルとして描いていて、中国ではこういうふうだということを書いているわけです。もともとにあるのは、中国文明への一つの憧れみたいなものがあって、それが源氏やらそういう王朝の文明というのを生み出すし、先ほど宋が滅んだ後、日本で中世が始まるわけですけれども、中世の文化というのもまた中国に対する一つの憧れで成り立っているわけです。
明治以降は御存じのとおり、ヨーロッパ・アメリカに対する一つの憧憬というか、お手本としてもらってきたというところがあるので、ものすごく外国に対して関心のあった人々が我々であるというのが一つです。
そういうふうにしていろいろ受け入れながら外国の文化の中でどうしても日本に根付かないものがあるわけですね。そういうものは捨てていかざるを得ない。だから、そこで選択が行われるわけなのです。
その選択の基準となったのは何かというふうに考えたとき、徒然草の55段でしたでしょうか、「家の作りやうは、夏をむねとすべし」という、兼好法師が書いている言葉があります。これを改めて問題意識をもって読んだとき、頭を殴られたような気がしました。
家の作りようだけではなくて、文化の作りようは、夏をむねとすべしと日本人は考えてきたのではないかと思ったのです。
「家の作りやうは、夏をむねとすべし」
長谷川様 外国からいろいろなものが入ってくるけれども、高温多湿の夏に耐えられないものは、結局捨てざるを得ない、そこで取捨選択が行われていたのではないかと思うのです、これが第2です。
第3に、この夏をどうにか耐えられるだろうと受け入れたものでも、よりよく夏を涼しく暮らせるような道具、あるいは様式に変えていく。
その働きがあって、簡単な例を言うと「うちわ」は、もともとは武将が蠅や蚊等の虫を追うためのものであったわけですが、それが日本に入ってきた途端に、風を起こす、涼しさを呼ぶ道具に変わっていく。そういう外国から受け入れたものを自分たちの暮らしの中で、涼しく暮らすための道具に次々に変えていく、これが日本人がやってきたことです。
うちわも大事なのですが、一番大事なのはもっと文化に関わるところで文字だと思うのです。日本にはもともといわゆる大和言葉と言われる話し言葉があったのだけれども、それを書き留めて記録する文字がなく、その間に中国から漢字が伝わってくるわけです。それを早速文字として使う。音は中国語の音があるから、それを日本語の大和言葉の音に合わせて漢字を使っていく。つまり漢字を発音記号のように使っていくのですね。
牧野先生 万葉仮名ですね。
長谷川様 万葉集はまさに万葉仮名だということで、原文は全部漢字ですね。かなり長い時間を過ごすわけですが、そこからカタカナ・平仮名が生まれてきます。その過程を考えると、誰が作ったかはわからないのですがカタカナ・平仮名が漢字から生まれてくる過程は、まさにこの蒸し暑い日本で漢字をしょっちゅう見ているのはとても大変であるという、日本人の生理感覚で、仮名が生まれてきたと僕は思うのです。平仮名の場合は書き崩しから出てきたわけでしょうし、漢字の場合は、人偏(にんべん)を取るとかそういう形で分解し、一部を採用するという形でカタカナが出てくるわけです。
どちらもやはり漢字に比べると格段に涼しげな文字ができ上がるので、これだと和歌がちゃんと読めるかなという感じで、いまだに漢字だらけだったらこれは大変ですね(笑)
牧野先生 それこそ暑苦しいですね(笑)
おっしゃっているように中国の書というのは楷書でも草書でも縦と横ははっきりしているのです。私もいろいろ見てきましたが、全部きっちりと書かれています。
これはやはり「天と地の間に私たちがいる」ということで、儒教もそうですね。亡くなってから「魄(はく)」と「魂(こん)」に分かれ、魂は天に行き、魄は地にかえり。天国はないので、そこにずっととどまる。年に1度魂降ろしをして現世にかえる。
ですから、天と地の間に住んで、地平線もはっきりしているので、天と地の縦の軸と横の地平線(軸)がはっきりしている中で、我々がい続けられているという感覚があります。そうすると文化や書も縦と横の軸がはっきりするのだろうなと思うのです。
それに対し、日本の平仮名はとても繊細でふらふらしているのだけれども、崩れていない、と思うのです。そこがとても興味深いなと思っていて。筆の使い方についても私たちは手首で動かすので、筆を全部おろさない、穂先と腹を少し使いますが、そういうこともさっき仰っていた“暑苦しくない”とか、あまり天地がはっきりしない中で生きているみたいなことも含めて、かかわってきているのかなという感じがしていました。
長谷川様 天と地があり、地平線があり、その真ん中に我々がいるのだという中国人の考え方は書にも反映していると思うのですが、それこそ中華文明の意識なのでしょう。自分たちこそ世界の中心だという中国人の意識があるのでしょう。
それに比べると、小野道風の継色紙やいろんな人でも仮名書の書というのはほとんど、陽炎みたいなものですね。海の波といってもいいですが、なんだからヒラヒラしている蝶々が飛んでいるようです。これでないと、日本人はやはり納得しないのではないのかもしれません。私はいろいろな書を表装して軸にしていて、漢字だけの漢詩もありますが、これはやはり相当見る側を緊張させますね。それに対して、歌でも俳句でも、上手でも下手でも、書で書いたものは和ませるという感じがあります。緩やかな、涼しげな感じの文字がとても良いなと普段から思っています。
私という中心があるから当然遠くは小さく見えるべきだというみたいな、遠近法ではない世界観というのは当然あるのではないかということだと思うのです。
長谷川様 また、長谷川等伯の松林図屏風、これは名作なのですが非常に不思議な絵です。
松の木を描いたというよりは、この空白を描くために、松を描いたような絵なのですね。松はもちろん素晴らしいが、その間のほのぼのとした空白。ここが得も言われぬ日本人を引きつけるものであるというふうに思うわけです。
牧野さんが仰っるように、墨の濃淡による遠近法なのだけども、西洋の1点透視図のような、あれとは全く違う。
どこにでも人が立って眺めるとこう見えるかなという感じで、いろいろなところへ入っていけるのです。
だから何か不思議な感じがするのは、そう見ていると、松の林の中を漂っている、さまよっているような感じがしてくるわけです。日本の絵というのはこれに限らず大体そういう風に描かれていて、視点が一つでないのですね。
那智の滝図という古めかしい縦長の絵がありますが、那智の滝が上から下までずっと描かれている上にお月さま?太陽?何かがあるのですね。それをいったいどこから眺めたのかと考えると、結局、空中に浮かんで視点をずらしながら描いていくのですね。滝を上の太陽や月からずっと下まで、そこに接するように描いていて、視点が移動しているわけです。
その他有名な北斎の富士山もそうですね。神奈川沖の絵がありますが、あれも波が逆巻いて、よく見ると波の曲線のところに船がへばりついている、そのずっと奥に富士山が浮かんでいる。あれも不思議な絵で、もちろん海側から見ている、あるいは神奈川沖といいますから、あの辺から見ているというのはわかるのですが、波の捉え方がそこへ近々と顔を近づけながら描いたような波であるし、船の上で身を寄せている人々の表情とか、あれも視点が動いているのですね。いくつもいくつも一つの絵の中に視点があって、そこが面白いですよね。
牧野先生 仰っているように、色々な視点から描かれてあるのですね。
少し難しい話になるかもしれませんが、アフォーダンスという言い方があって、私たちは自分が立っていると思っているけれども、本当は立たせられているのだと捉えたらどうか、と言う考え方です。
例えば私たちはこの地面に立っているのだけども、実は地面に立つように地面から支えられて、そこにあるのだというふうに捉えたら視点が変わるのではないかとか、遠くを見ていて、遠近法で一点透視図のような形で見えることになっているのだけれども、目がここにあって錯視をしていると言われるのだけど、本当だろうか?たった10センチぐらいの距離が錯視をつくり出すぐらい、そんなに効果があるのかというと、どうもそうではなくて、私たちは目とか体で光のキメを感じ取っているのではないか。
そういう議論が今あって、そうすると、このキメが粗いところと細かいところで距離を測るのではないかということになると、等伯が描いているような遠近というのは、実はそのキメの粗さとか細かさによってと前後があるのだという風に受けとめるみたいな。
そうなると環境からそう見えるようにさせられて、私たちはそこに立っている、立つことができるようになっている。
そう見ていくとむしろ西洋が今までやってきたような、私という中心があるから当然遠くは小さく見えるべきだというみたいな、遠近法ではない世界観というのは当然あるのではないかということだと思うのです。
私たちが学校で習うのは遠近法なので、写生に行って見たままに書くようにと先生に言われても「こんなに見えるわけがないだろう」とも言われるわけです。
遠くのものは遠くに見えるはずだし、そこから1点に来ているはずだから、お前が描いているものはおかしいとよく言われたのですが、そう見えるようになってしまうのですね。ですけれども、本当はそうじゃないのかもしれないということなのです。
長谷川様 西洋の遠近法というのは、まさに今では正しい物の見方のように言われるけれども、実は極めてヨーロッパ的な、しかもヨーロッパのある時代の一つの世界観の基本になった考え方ですね。だから、全体から見ると一つのヨーロッパという地方の、一つの世界観をこの150年間、日本人は一生懸命真似しようと健気にも努力しようとしてきたのかもしれないわけですね。
牧野先生 それが所謂工業社会といいますか、ここ150年間の物質的な発展をもたらしたと思うのです。それが日本というこの地で非常にうまくいった。
過去に高度経済成長があったと思いますが、頂点に達したところで、どうするかという余韻が出てくる中で、今改めて和ということが、ある意味でブームになっていると思うのですが、それは先ほど長谷川さんおっしゃったように、ある種いいことではありながら、危ない面もある。
和というものが、これからどういう形で展開したらいいのかというのは、ではもともと和というのは何だったのかということを、もう少し日本中心主義ではなく、和という思想そのものが一体何だったのかといったことをもう少し突き詰めていく必要があるとおっしゃっているのではないかと思い、受け止めました。
長谷川様 ちょうどそれをやるいい時期に差し掛かっていると思います。150年という時間は逆にいうとここを逃すと大変なことになってしまう恐れがあるから、本当に今の時代をきちんと生きていた方がいいと思います。
